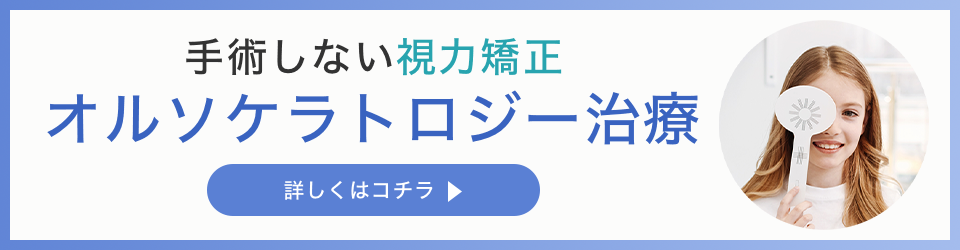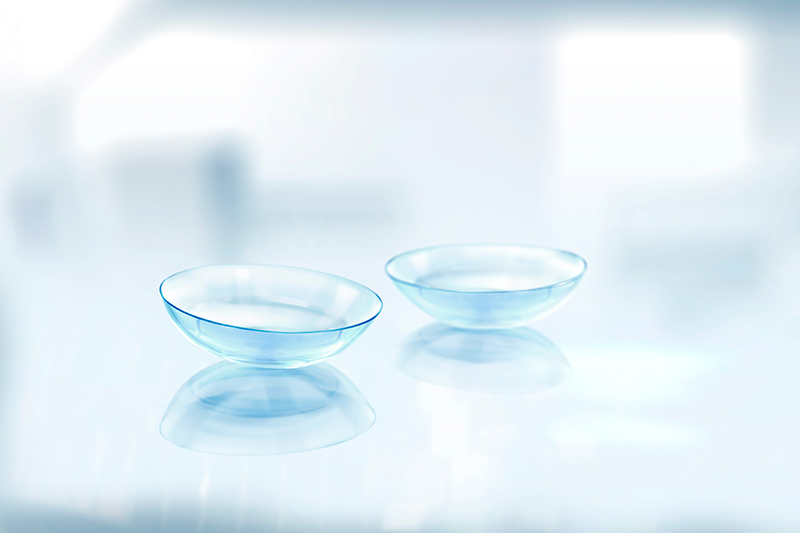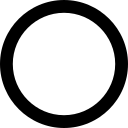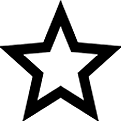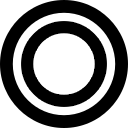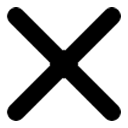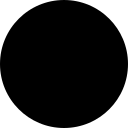近視とは
近視とは、目の奥行きが長いために、網膜でピントが合うべき位置が前方にずれ、遠くが見えにくくなる状態を指します。近視は遺伝と環境の両方が影響していると考えられています。近視には単純近視と病的近視の2種類があります。単純近視は、眼鏡やコンタクトレンズで矯正することができます。一方、病的近視は眼球の後ろが突出して変形し、網膜や視神経に病的な変化を来すリスクが高くなります。このようなことが生じてしまうと眼鏡やコンタクトレンズでは矯正できなくなります。
症状
単純近視では、遠くが見えにくく、近くの物は比較的見やすい状態です。対して、病的近視では、突然の視力低下や、物が歪んで見える、遠くも近くも見えにくいといった症状が現れることがあります。病的近視は視力の急激な悪化を伴うことがあり、慎重な対応が必要です。
治療方法
単純近視には眼鏡やコンタクトレンズによる視力矯正のほか、睡眠中に特殊なコンタクトレンズで角膜の形を矯正するオルソケラトロジーや、視力改善のためのLASIK(レーシック)、眼内コンタクトレンズ(ICL)手術があります。病的近視の治療では、病状に応じて抗VEGF薬の眼内注射や硝子体手術などが行われることがあります。これらの治療は視力を維持し、病状の進行を防ぐために重要です。
リジュセア®ミニ点眼液
当院では、「リジュセア®ミニ点眼液」を導入しております。リジュセア®は、眼球の前後の長さが伸びるのを抑えることで、近視の進行を抑制することが期待できます。ミニサイズの使い切りタイプで衛生的にご使用いただけるのも特徴です。詳細は下記のPDF資料をご覧ください。
「リジュセア®ミニ点眼液」について(PDF:777KB)